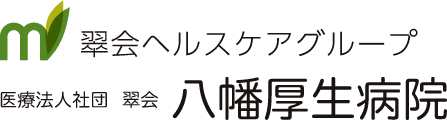EATING DISORDER
摂食障害治療
MENU

摂食障害とは?
EATING_DISORDER
・「食事を食べること」またはそれに関連した行動の持続的な障害のことです。 “拒食症”、“過食症”と一般に呼ばれる病気がその代表例となります。
・神経性やせ症も神経性過食症も“強いやせ願望・肥満恐怖による食行動異常”です。一番の違いは低体重状態が持続しているかどうかです(無月経は低体重によって生じるだけということで診断基準からはずされました)。
・神経性やせ症の患者さんは低体重状態が持続しており、それにも関わらずちょっとした体重増加を恐れます。体重のコントロールに失敗して少しでも体重が増えると「自分はだめな人間」と考えます。
・神経性やせ症には二つのタイプが存在し、食事制限のみで低体重を維持する方は「摂食制限型」、過食(通常よりも明らかに多い食べ物を制御出来ずに食べる行為)や排出行為(自己誘発性嘔吐、下剤・利尿剤・浣腸の乱用など)を伴う方は「過食・排出型」と呼ばれます。
・神経性過食症は、強いやせ願望・肥満恐怖を持っているにも関わらず、食事制限ができず過食が始まって体重が正常範囲となり、肥満を防ぐために排出行為を行う様になった方です。そしてうまく減量出来ない自分を「ダメな人間」と考えます。
・長年の経過の中で神経性やせ症、制限型→神経性やせ症、過食・排出型→神経性過食症などと病型が変化する患者さんもいます。

代表的な摂食障害の特徴
TYPICAL FEATURES
|
神経性やせ型 (摂食制限型) |
神経性やせ型 (過食排出型) |
神経性過食型 | 過食性障害 |
回避制限性 食物摂取症 |
|
| 特徴 |
体重や体型の感じ方の障害があります。 やせていても太ってると感じます。 |
体重や体型の感じ方の障害があります。 やせていても太ってると感じます。 |
体重や体型の感じ方の障害があります。 過食に苦痛を感じ、罪悪感を伴います。 |
体重や体型の感じ方の障害があります。 過食に苦痛を感じ、罪悪感を伴います。 |
体型や体重へのこだわりやボディーイメージの障害を伴わない。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事 | 食事量を制限します。 | 過食する方もいます。 | 食事量のコントロールができず、頻繁に過食します。 | 食事量のコントロールができず、頻繁に過食します。 | 食事量の減少、偏食、食事の拒否、嚥下恐怖 等 |
| 瘦せるための行動 | 過度に運動したりします。 | 食べ物を吐いたり下剤を使ったりします。 | 食べ物を吐いたり下剤を使ったりします。 | 食べ物を吐いたり下剤を使ったりしません。 | 過活動や嘔吐・下剤の使用は一般的に認めません。 |
| 体型 | 明らかな低体重 | 明らかな低体重 | 正常または過体重 | 正常または過体重 | 低体重から正常 |