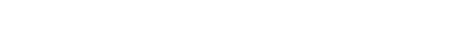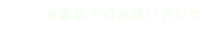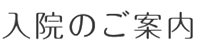摂食障害治療について
摂食障害とは?
- 「食事を食べること」またはそれに関連した行動の持続的な障害のことです。 “拒食症”、“過食症”と一般に呼ばれる病気がその代表例となります。
- 神経性やせ症も神経性過食症も“強いやせ願望・肥満恐怖による食行動異常”です。一番の違いは低体重状態が持続しているかどうかです(無月経は低体重によって生じるだけということで診断基準からはずされました)。
- 神経性やせ症の患者さんは低体重状態が持続しており、それにも関わらずちょっとした体重増加を恐れます。体重のコントロールに失敗して少しでも体重が増えると「自分はだめな人間」と考えます。
- 神経性やせ症には二つのタイプが存在し、食事制限のみで低体重を維持する方は「摂食制限型」、過食(通常よりも明らかに多い食べ物を制御出来ずに食べる行為)や排出行為(自己誘発性嘔吐、下剤・利尿剤・浣腸の乱用など)を伴う方は「過食・排出型」と呼ばれます。
- 神経性過食症は、強いやせ願望・肥満恐怖を持っているにも関わらず、食事制限ができず過食が始まって体重が正常範囲となり、肥満を防ぐために排出行為を行う様になった方です。そしてうまく減量出来ない自分を「ダメな人間」と考えます。
- 長年の経過の中で神経性やせ症、制限型→神経性やせ症、過食・排出型→神経性過食症などと病型が変化する患者さんもいます。
病的な低体重ってどれくらい?
体格指数(Body mass index: BMI)という尺度が国際的には一般的です。 BMIは体重(kg)/身長(m)2で計算される値で22kg/m2が標準値です。
身長158cmの人であれば、標準体重は1.58×1.58×22となり、54.9 kgとなります(以下すべての計算は小数点第二位を四捨五入して表記)。 また、国際保健機関(WHO)は成人の正常下限をBMI 18.5 kg/m2としています。1.58×1.58×18.5となり、46.2 kgが正常下限の体重と言うことになります。 ただ、日本人は欧米人に比べて小柄であるため、もう少し低めであるという議論も存在しています。それをBMI 17.5~18 kg/m2程度と考えても、日本人の場合でも少なくとも43.7~44.9kg未満は注意が必要でしょう。 また、我が国では以下のような低体重時の活動制限の指針が設けられています。難病情報センターホームページより
| 標準体重 | 身体状況 | 活動制限 |
|---|---|---|
| 55%未満 | 内科的合併症の頻度が高い | 入院による栄養療法の絶対適応 |
| 55~65% | 最低限の日常生活にも支障がある | 入院による栄養療法が適切 |
| 65~70% | 軽労作の日常生活にも支障がある | 自宅療養が望ましい |
| 70~75% | 軽労作の日常生活は可能 | 制限つき就学・就労の許可 |
| 75%以上 | 通常の日常生活は可能 | 就学・就労の許可 |